私は嗜好・医療目的の大麻が合法な国であるアメリカ、カナダ、オランダ、タイにて、大麻を利用している人を多く目にしてきました。
アメリカ、カナダでは、店でIDを見せるだけで酒やタバコと同じように大麻が買えます。
日本では所持しているだけで逮捕されるのに、なぜアメリカをはじめとする合法国では、若者から老人まで大麻を吸っていいのでしょうか。
そういった背景から日本人の固定概念にある「大麻=ダメ。ゼッタイ。」は真実なのか、なぜ日本では法で禁止されているのか疑問を持ちました。
世界的には大麻の合法化が進んでいる国が増え、2020年のアメリカでは合法大麻の売上が約3兆円 に及ぶなど、大麻が一大ビジネスになっている国さえ存在しています。
その市場規模は今後10年で7〜8兆円 になる試算もあり、その大規模な市場は「グリーンラッシュ」とも呼ばれ、各国が規制緩和に動いています。
昨今の日本においても、一部の政治団体は医療用大麻の解禁を主張し、医療用大麻の合法化の検討が進んでいます。
固定概念、遵法精神が強い私たち日本人は大麻についての理解が少なく、何が有害/無害、違法/合法であるかを適切に判断しているとは言い難いでしょう。
そこで「大麻」とはなにか、いつ、なぜ、どのように法で禁じられたのか、そしてなぜいま日本で「大麻解禁」を検討し始めたのかについて考察していきましょう。
大麻とはなにか

大麻とは「大麻草」から作られるもので、様々な名称(ハッパ、マリファナ、ガンジャなど)で呼ばれています。
精神依存性があり、日本では大麻取締法によって規制されています。
また大麻の使用用途には「産業用・医療用・嗜好用」に分けられ、現在日本では「産業用大麻は合法」、「 医療用・嗜好用大麻は非合法」になっています。
大麻には数百種類のカンナビノイド(「大麻草」に含まれる生理活性物質の総称)が含まれており、大別するとCBD(カンナビジオール)とTHC(テトラヒドロカンナビノール)の2つがあります。
THC(テトラヒドロカンナビノール)はハイになり、中毒性があります(非合法)。
144種類ある大麻草の独自成分カンナビノイドのうち、最も向精神作用のある成分であり、いわゆるマリファナの主成分として知られています。
痛みの緩和、吐き気の抑制、けいれん抑制、食欲増進、アルツハイマー病への薬効があることが知られています。
一方CBD(カンナビジオール)は深いリラックス作用が得られます(合法)。
144種類ある大麻草の独自成分カンナビノイドのうち、向精神作用のない成分で、癲癇の他に、アルツハイマー病、パーキンソン病、多発性硬化症、神経性疼痛、統合失調症、社会不安、抑うつ、抗がん、吐き気抑制、炎症性疾患、関節リウマチ、感染症、クローン病、心血管疾患、糖尿病合併症などの治療効果を有する可能性があると報告されています。
またCBDは、大麻草に含まれる成分の1種だが、違法性はありません。
麻に含まれる禁止成分であるTHCが含まれる製品は、日本国内では販売の許可がおりていません。
国内で販売されているCBD製品は、厚生労働省の許可を得た合法のものになり、CBDを愛用している芸能人も多く、ローラ、高橋愛、ダイヤモンドユカイ、武尊などに利用されています。
効用としては、ストレス解消や睡眠導入、腸の働きの補助、疲労回復、また生理痛やPMS(月経前症候群)など、女性の症状改善も期待されています。
また医療用大麻の効果として主に以下が挙げられます。
① 抗がん剤の副作用を緩和 ② うつ病を緩和 ③ 緑内障による失明を防止
④ 癲癇の発作を防止 ⑤ PTSDを解消 etc.
また現代社会では大麻以外にも、様々な違法薬物が流通しています。
そこで主な薬物を取り上げ、以下に記載します。
*コカイン・・・クラック(麻薬)
無色ないし白色の粉又は結晶性粉末(化学調味料のような感じ)で、麻薬に指定されている強い精神依存性を有する薬物。
(俗称の事例:コーク、コーラ、スノウ、ノーズキャンディなど)
*大麻
「大麻草」から作られるもので、様々な名称で呼ばれている。精神依存性がある。
(俗称の事例:ガンジャ、ハシッシュ、ブッダスティック、ハッパ、チョコ、野菜など)
*ヘロイン(麻薬)
「あへん」から作られた薬物で、化学名では「ジアセチルモルヒネ」と呼ばれている。強い鎮痛作用がある反面、すぐに依存性が生じ、その依存性は極めて強い。
(俗称の事例:スマック、ジャンク、ホース、ダスト、チャイナホワイトなど)
*LSD(麻薬)
強い幻覚作用があり、精神に障害を起こす事例もある。
(俗称の事例:アシッド、ペーパー、タブレット、ドラゴンなど)
*覚醒剤
一般にアンフェタミン、メタンフェタミンの2種類の興奮剤を指す。見かけは粉砂糖を砕いたような無色透明のかたまりで、匂いはない。水に溶けやすい性質を持っており、静脈注射や加熱によるガスの吸入、ジュースなどに溶かして飲むなどの方法によって摂取されている。強い依存性があり、精神や身体をボロボロにしてしまう。大量に摂取すると死に至る場合もある。
(俗称の事例:アイス、ハーツ、ホワイト、スピード、エス、クリスタルなど)
*その他の薬物
・MDA(俗称:ラブ・ドラッグ)、MDMA(俗称:エクスタシー)、PCP(俗称:エンジェル・ダスト)、メスカリン、マジックマッシュルーム等、多くは幻覚作用を持ち、薬の形も粉末、錠剤、カプセル、液体等様々な形がある。これらの薬物は、錯乱状態になり殺傷事件を起こしたり、薬がきれた後でも突然に錯乱状態の発作を起こすこともあり、危険なもので、日本では法律で規制されている。
・シンナー・トルエン(有機溶剤)
シンナーは塗料のうすめ液として使われ、有機溶剤の混合物。その主成分がトルエンであり、特有なにおいを持つ無色透明の液体で、揮発性、引火性が高い。乱用すると、頭痛、はきけ、めまい、全身倦怠感などの症状が見られる。また、脳細胞を破壊するため、乱用を続けると大脳は萎縮し、たとえ乱用を止めても元には戻らない。歯は溶けてボロボロになる。長期間乱用すると、シンナー、トルエンを吸入していない時でも、実在しないものが見えるなどの幻覚や被害妄想などが現れる。過度に吸入した場合は、呼吸中枢が麻痺し、窒息死することもある。
・危険ドラッグ
危険ドラッグとは、多幸感や快感を高めると称し、興奮や幻覚作用等を有する成分を含むものをいい、「ハーブ系」、「リキッド系」、「パウダー系」等の種類がある。いずれも、合成カンナビノイドという大麻類似の成分や麻薬・覚醒剤類似の成分などを含むため、一般のハーブ、アロマ等とは全く異なる極めて危険な薬物。
日本における大麻の歴史と現状
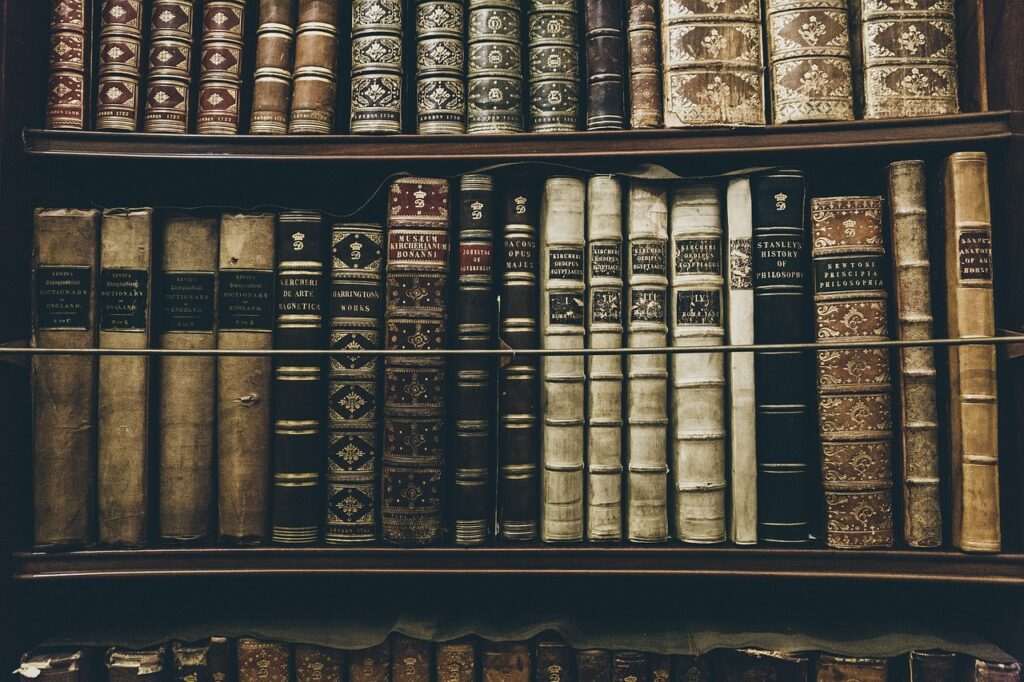
では日本ではなぜ大麻を禁止しているのか、日本における大麻と大麻規制の歴史を振り返りましょう。
今では法律で禁じられているが、戦前は大麻が自由に栽培されていたのです。
江戸では、大麻は紅花、藍に並ぶ「三草」と呼ばれる生活を助ける民間必需とされた草の一つで、様々な用途で利用されていました。
日本敗戦後の1945年、日本はポツダム宣言を受諾し、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の占領下に置かれ、同年10月12日、GHQは「日本に於ける麻薬製品および記録の管理に関する件」という覚書を発行しました。
麻薬の定義は「あへん、コカイン、モルヒネ、ヘロイン、マリファナ(カンナビス・サティバ・エル)、それらの種子と草木、いかなる形であれ、それらから派生したあらゆる薬物、あらゆる化合物あるいは製剤を含む」とされ、当時の厚生省はこの指令に基づき11月24日、厚生省令第四六号「麻薬原料植物の栽培、麻薬の製造、輸入及輸出等禁止に関する件」を交付しました。
当時専業の大麻農家も少なくなかったため、数万人規模で農家の困窮が起き、大麻農業は壊滅的な打撃を受ける危険がありました。
そこで農林省は1946年11月に農政局長名で、終戦連絡事務局に大麻の栽培許可を要望し、全面的な禁止を回避し、「農作物としての大麻」を守ろうとしました。
その結果、1947年2月、連合軍総司令官より「繊維の採取を目的とする大麻の栽培に関する件」という覚書が出され、一定の制約条件の下、大麻栽培が許可されました。
翌年の1948年、GHQの指導により日本では「大麻取締法」が制定され、大麻の使用が一切禁止になったのです。
同時に「麻薬取締法」が制定されたが、これは農家が取り扱う従来の農作物としての大麻と、医師などが取り扱う麻薬類を分けるための措置でもあったのです。
ではなぜGHQは一切の大麻の使用を禁じたのでしょうか。
そもそも通常の法律は「総則」の冒頭に制定の「目的」が書かれているます。
しかし、大麻取締法にはこの目的が書かれていないまま70年以上が経過しているのです。
この法律の最も大きな問題とも言えます。
そのため明確な目的はいまだに不明だが、様々な説があります。
それは当時、大麻文化が国民文化と密接に結びついていたからだと言われています。
神社ではしめ縄として使っているなど、神事の場面で麻を使われることが多かったのです。
そこでGHQは日本の大麻文化は国家神道と結びつき、この国家神道と軍国主義が密接に結びついていると考え、大麻の使用を一切禁止にしました。
つまりGHQによって「二度と戦争を起こさないように」という思いから法が制定され、今日の日本にも残っているのです。
戦後当初、大麻農業の保護を目的として制定された大麻取締法はいつの間にか「違法な薬物」を取り締まるための法律として機能するようになりました。
そして、農作物という側面が忘れ去られた大麻は、覚醒剤、コカイン、ヘロインなどのハードドラッグとひとくくりにされ、「人間を廃人にする大麻の害悪」というような薬物教育の授業が定着しました。
そんな学校授業が30年間も続いてきたのですから、現在の日本に大麻への異常な拒否感が根付くのは当然と言えるでしょう。
日本では、大麻取締法、覚醒剤取締法(覚醒剤の乱用による保健衛生上の危害を防止するため必要な取締り)、あへん法(あへんの供給の適正を図るため必要な取締り)、麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)(麻薬・向精神薬乱用による保健衛生上の危害を防止するため必要な取締り、麻薬中毒者の措置)、毒物及び劇物取締法(シンナー)(「薬物5法」と呼ばれる)という主要な薬物を取り締まる法律が存在します。
麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料、けし、あへん、大麻、覚醒剤、覚醒剤原料、指定薬物といった規制対象物質に応じて、それぞれの取締りを目的とした法律です。
上記の麻向法及び覚醒剤取締法は成分規制ですが、現行の大麻取締法は大麻草の部位によって規制をかけています。
具体的には成熟した茎や種子を除く花穂、葉等が規制対象となっています。
また麻向法、あへん法、覚醒剤取締法、医薬品医療機器等法の各法律には、みだりに所持、施用・使用した場合の罪が規定され、制定当初から所持に対する懲役・罰金に係る罰則と同様の罰則が使用に対しても規定されています。
一方、大麻取締法には所持に対する罰則は規定されているが、使用に対する罰則が規定されていません(2023年12月6日法改正前)。
では大麻の使用自体は違法ではないのか。
大麻取締法は大麻の所持・栽培・譲り受け・譲り渡し、そして研究のための使用を無許可で行うことを禁止しています。
覚せい剤取締法では覚せい剤の使用を禁止し、麻薬及び向精神薬取締法は免許を受けた麻薬研究者以外の施用、受施用を禁止しています。
大麻取締法にだけ「使用」と記されていません。
では大麻の使用自体は違法ではないのか。
またなぜ大麻取締法にだけ「使用」と記していないのか。
大麻草の花や葉っぱにTHC成分を含む樹液が多く含まれていますが、成熟した茎や種子にはTHC成分はほとんど含まれていません。
よって規制対象から排除されています。
また大麻の茎は麻織物、麻縄、繊維になり、大麻の種子は七味唐辛子に含まれています。
そのため、尿として排出されたものが大麻の茎、種子なのか、花、草の部分なのか特定することができないのです。
よって使用罪は処罰範囲から除外されています。
しかし所持、譲り受け、及び譲り渡しにより処罰の対象となる場合がほとんどです。
※2024年12月12日から「麻薬及び向精神薬取締法」で「使用」も禁止になっています。
では海外で使用するのは合法なのか。
日本人の留学生が大麻合法国に留学、旅行に行った際、大麻を興味本位で利用する人も多いのではないでしょうか。
日本国内での大麻は非合法であるが、日本人が合法国で利用することは合法なのでしょうか。
法律から紐解いていきましょう。
大麻取締法の第24条は「大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸出し、又は本邦若しくは外国に輸入した者は、七年以下の懲役に処する」、第24条の8では「第24条、第24条の2、第24条の4、第24条の6及び前条の罪は、刑法第2条の例に従う」と記され、刑法第2条は「すべての者の国外犯」を規定したものです。
この規定によって、大麻の栽培や所持などの罪を国外で犯したとしても、大麻取締法の適用が認められます。
一方で賭博の法律である刑法185条では「賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし海外の(合法的)カジノでギャンブルを行っても、日本の刑法を適用するという規定はない」と記され、海外でのカジノ、ギャンブルは法に問われることはありません。
「刑法第2条の例に従う」とはなにか。
それは、日本は相手国と協調して大麻の取締りに当たるという決意の表明です。
また大麻取締法第24条の8が規定している犯罪は「大麻を[みだりに]栽培、所持、日本や外国に輸出入するなどの行為」です。
では「みだりに」とはどういった意味なのか。
「みだりに」とは違法性を意味する言葉で、日本国内の場合は日本法に違反すること、一方日本国外の場合は、行為が行われた国の法令に違反する&行為が日本で行われたとすれば、日本法にも違反することです。
つまりこの大麻取締法第24条の8が規定している犯罪は、日本だけではなく、その国でも違法性を有し、処罰可能でなければいけないのです。
しかし大麻合法化した国内で完結している大麻の購入や所持などは合法であり、形式的に大麻取締法が規定している行為であっても日本法から見て「みだりに」行われたものではないと考えるべきです。
また例外も存在し、刑法第3条では「この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する」と記しており、放火や文書偽造、強制性交や強制わいせつ、殺人や傷害致死などの犯罪については、日本人が海外で犯した場合であっても日本の刑法も適用されます。
大麻に対する認識や意識
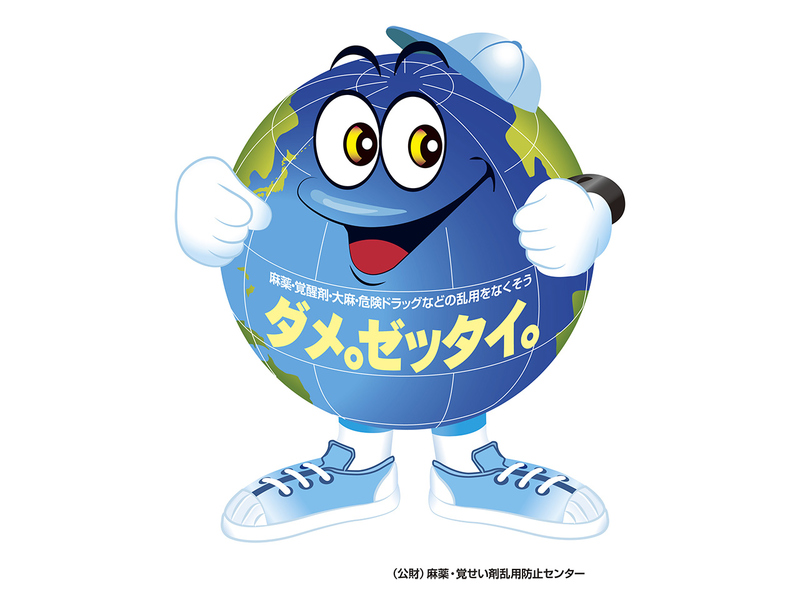
”https://donation.yahoo.co.jp/detail/1886001”
薬物乱用未然防止活動 キャンペーンキャラクター「ダメ。ゼッタイ。」君
上の写真、「ダメ。ゼッタイ。」という薬物乱用防止を訴えるキャッチコピー、そのキャッチコピーが入っているパンフレットなどを聞いたり見たことはありますでしょうか。
ではどれだけの人が大麻の違法性を認識し、有害性を正しく理解しているのか、調査の結果を見ていきましょう。
① 大麻に対する危険(有害)性の認識
2022年の警視庁の調査によると、覚醒剤に対する危険(有害)性の認識は、「あり(大いにあり・あり)」と答えた人は74.2%であった一方、大麻に対する危険(有害)性の認識は、「あり(大いにあり・あり)」と答えた人は14.3%で、「なし(全くない・あまりない)」と答えた人は79.5%といった結果になり、覚醒剤に対する危険(有害)性の認識と比較すると、危険視している割合は著しく低い。
特に10代においてはその割合が 2017年の48%から2020年では78.5%と大幅に高くなっている。
なぜ若者をはじめ、人々は大麻に対する危険性を軽視しているのか。
その情報源として「友人・知人」「インターネット」が80%近くを占めている。
ここでもSNSなどのインターネットが大麻に対する危険性の軽視を助長していることがわかります。
② CBD(カンナビジオール)の理解
大麻の有害成分であるTHC(テトラヒドロカンナビノール)を含まないとされる CBD(カンナビジオール)製品についても、好奇心や誘いから軽い気持ちで嗜好品としてそれらを使用する者が、何が有害/無害、違法/合法であるかを適切に判断しているとは言い難い。
CBDに関する情報を発信するメディアである STOKE 社が 2021 年に日本全国の 20〜70 歳を対象に行ったアンケートによると、CBDを知っていると回答したのは100名中34名と認知度は低い。
またCBD製品に対する違法性の認識も低く、CBD 製品の使用・所持・譲り渡し・譲り受けをするとすべて罰せられると考える大学生は1年生44.0%、3年生30.4%、大麻の使用・所持・譲り渡し・譲り受けをするとすべて罰せられると考える大学生は1年生63.0%、3年生66.1%であり、比較すると、CBD製品について「すべて罰せられる」と考える学生の割合は低かった。
また2021年の立命館大学で行われた大麻・CBD(カンナビジオール)製品に関する薬学生への意識調査ではCBD製品に関する情報をインターネットから得ていると答えた割合が比較的高く、3年生においては学校、大学、テレビ、ラジオを上回っている。
つまりCBD 製品について知る学生は、教育の一環として知識を身につけているというよりは、むしろ自主的にインターネットを検索することにより情報を得ていると考えられます。
またGoogle で「大麻」を検索すると厚生労働省や警察庁の大麻乱用防止に関する情報が上位に上がるが、「CBD」を検索した場合、CBD製品の安全性に着目した情報が上位に上がり、その多くは製品の購入のための情報にリンクされています。
化学的に合成された CBD や「大麻」に該当しない CBD 成分であれば使用、所持、譲り渡し・受けが罰せられることはないが、学生の大部分が CBD 製品について大麻と似たようなものであるとの曖昧な認識のまま、学校・大学で適切な学びを経ず、最初に得る情報がショッピングサイトの情報である状態は好ましいとは言えないでしょう。
③ 関西四大学の薬物に関する意識調査
これまで大学生の大麻等不正薬物の所持・乱用による事件事故が相次いで発生し、薬物汚染が大きな社会問題に発展しました。
こうした状況の下で、各大学における薬物に関する教育活動が喫緊の課題となり、2009年3月7日に関西大学、関西学院大学、同志社大学、立命館大学の関西四大学は、薬物乱用防止に関する共同声明を発表しました。
活動の一つとして、2009年10月から関西四大学共同の「薬物に関する意識調査」を開始しました。
そこで2022年度の調査結果を見ていく。この調査は、2022年度関西四大学入学生(27,424名)を対象者として、回答数は18,847名(69%)である。
④ 薬物の名前の認知度
薬物の名前のうち、一番認知度があるのは大麻で92.0%、次いで覚醒剤は85.2%である。
他にもコカイン、MDMAなどの薬物の認知度も5割を超えているものの、LSD以外のすべての薬物の認知が、前年より下がっている。
⑤ 使用することへの印象
「これらの薬物を使うことについてどのように考えているか」という問いに対し、「どのような理由であれ、絶対に使うべきではないし、許されることではない」という回答が88.9%だったが、「1回位なら使ってもかまわない」「使うかどうかは個人の自由」と考えている学生が一定数存在していた。
⑥ 薬物の勧誘
「薬物を使用することや購入することを誘われた、または勧められたことがあるか」という問いに、「誘われた、または勧められたことはない」という回答が93.5%、一方で「購入を勧められたことがある」「使用を誘われたことがある」「無理やり使わされたことがある」と回答している学生も一定数存在しました。
⑦ 周囲の所持者、使用者
「周囲に薬物の所持、使用している(いた)人がいたか」という問いでは、「いない」という回答が89.1%と多かったものの、「いる(いた)」「わからない」が前年より増加している。
また「いる(いた)」「わからない」の回答者からの調査では、大麻の取り扱いが54.0%と最も高かった。
一方で覚醒剤が増加傾向にあることも分かった。
⑧ 大麻の入手先
「これらの薬物を入手可能と考えますか」という問いに、入手可能と考えている人(「難しいが手に入る」「手に入る」)の割合が38.3%と高く、前年度と比べても増加している。
またこれらの回答者が入手可能と考えた理由について、9割以上が「SNSやインターネットで探せば見つけることができると思うから」と答えている。
これらの調査結果では、薬物の危険性を軽視している人、友人、知人が使用している(していた)人の割合は少ない。
しかし友人、知人が使用している(していた)人の割合は前年度より増加していることや、覚醒剤の取り扱いが増加していることなど、目に留まるものがありました。
これまでの調査結果でも分かるように、大麻に対する好奇心、勧誘を受けやすいのは20代が一番多い。
今回の調査対象は新入生であったが、今後彼らの大学生活で、インターネットの誤った情報、周りからの悪影響を受ける場合もあります。
そこで上回生を対象にした調査も必要であると考えています。
また今回の調査でもSNSやインターネットが大麻などの薬物と密接に関わっていることが分かり、SNSやインターネットの発展、使い方については再度検討する必要があるのではないでしょうか。
世界の大麻の歴史と現状
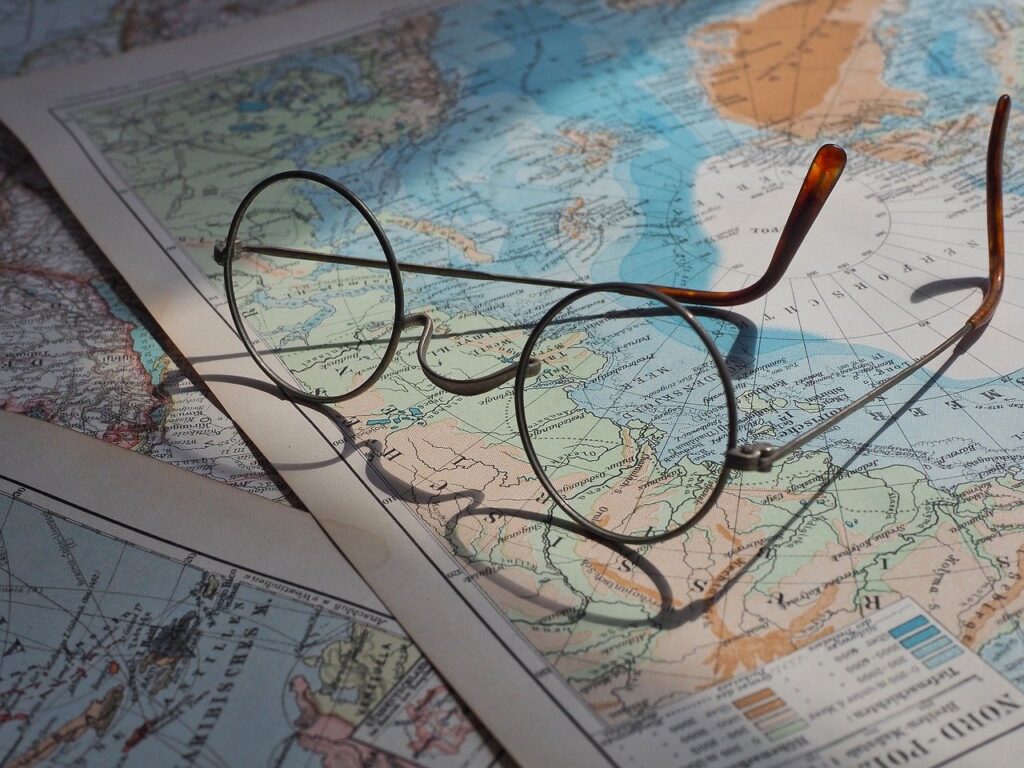
大麻が合法化されている国はどこなのでしょうか。
また、それらの国における大麻の使用用途に関する規制について、表1に示しました。
表1. 各国における大麻の規制一覧
| 対象国 | 娯楽使用 | 医療使用 |
| カナダ | 合法 | 合法 |
| ウルグアイ | 国内居住者のみ合法。栽培は6株まで | 合法 |
| アメリカ | 17の州、2つの準州、コロンビア特別区では合法化されているが、連邦レベルでは違法となっている。 | 36の州、4つの準州、コロンビア特別区では合法化されているが、連邦レベルでは違法 |
| オランダ | 政府認定のショップでの使用と販売は許可。5グラム以下の大麻の所持を非犯罪化。 | 合法 |
| ブラジル | 違法だが少量所持については非犯罪化。罰金のみ | 終末期の患者や治療法が他にない患者には合法 |
| メキシコ | 5グラムまでは非犯罪化 | THC1%以下であれば合法 |
| タイ | 違法 | 合法 |
| オーストラリア | ノーザンテリトリーと南オーストラリア州で非犯罪化。 オーストラリア首都特別地域では個人の使用は合法だが販売はできない。 | 連邦レベルおよびすべての州で合法。ただし資格条件やその他の詳細は州によって異なる |
| イスラエル | 非犯罪化 | 合法 |
| 韓国 | 違法 | 合法 |
上記の表にある非犯罪化とは従来犯罪とされてきた行為を非犯罪化し、処罰しないものとすることである。
上記のように世界では大麻の合法国が多くあります。
そこで各国における大麻の合法化までの経緯についてみていきましょう。
① アメリカ
アメリカでの大麻合法化は様々な理由があるが、大別して、次の2つが挙げられます。
一つ目はアメリカの「合理性」によるものです。
アメリカでは大麻が合法化になる以前から、大麻は手軽にアクセスできるドラッグの一つでした。
世論調査では1985年が30%、2021年は49%の人が大麻を使用した経験があるとの結果でした。
またオバマ元大統領が過去に大麻を使用したことを告白するなど、大麻は違法なドラッグでありながら、事実上、非常に身近なものでした。
それと同時に違法な大麻の販売も活発であり、犯罪組織に資金が流れるようになったうえ、粗悪な大麻の流通、大麻の乱用や未成年者による使用が防げないという面もありました。
そこで、大麻市場を放置せず、大麻を合法化することで積極的に大麻市場をコントロールするということが考え出されたのです。
大麻を合法化すれば、税収も増えるうえ、その分、ブラックマーケットに流れるお金を減らすことができる。
また、大麻に関する犯罪に割くリソースを省略でき、州としての経費の削減、粗悪な大麻の利用や大麻の乱用、未成年者による使用を防ぐことで医療分野の経費も削減できます。
もちろん、その決定にあたっては、このような経済的な理由だけではなく、アルコールやタバコとの有害性の比較という視点からの検討もあったが、いかにもアメリカらしい「合理性」が合法化を加速したことは間違いないでしょう。
二つ目は大麻犯罪検挙の裏側にある人種差別です。
アメリカでは黒人と白人の大麻所持率は大きな差がないにもかかわらず、黒人は白人に比べて、逮捕される可能性は3.73倍高いというデータがあります。
つまり、アメリカでは有色人種を逮捕するため大麻が利用されていたのではないか、ということが背景としてあったのです。
人種差別に対する反対運動が強まったアメリカにおいて、大麻が人種差別に利用されているという事実は、大麻の合法化を後押ししたことは間違いないでしょう。
② オランダ
次に世界中から大麻目的の観光客を集めるオランダを見ていきましょう。
オランダ国内でも特に首都アムステルダムでは大麻の取引や使用が盛んで、「コーヒーショップ」と呼ばれる大麻販売店が数多く街に並び、店舗の立地や大麻製品の取引量など、厳格な条件を満たしたコーヒーショップのみが、大麻の売買を許可されています。
以上のようにオランダでは多くの観光客を集めているものの、オランダ政府は1976年の法改正で、5グラム以下の大麻の所持を非犯罪化しています。
これにより、大麻の嗜好目的の使用は「違法だが起訴されない」という、いびつな法制度が出来上がったのです。
ではなぜオランダ政府は非犯罪化に法改正したのでしょうか。
それは1960年代後半から70年代にかけ、ヒッピー文化の世界的な広がりとともに、欧州では若者が薬物乱用に走るようになったことが原因です。
オランダで薬物取り締まりの見直しが高まった頃には、すでに大麻はアルコールと同じくらい庶民に身近な消費の対象となっていて、大麻の使用者に処罰を下す「抑圧政策」をとれば、大麻などのいわゆるソフトドラッグはハードドラッグと呼ばれるヘロインやコカインなど中毒性の高い薬物と同じ市場に流通することになります。
そこで、コーヒーショップという形で正規の大麻流通ルートを確保することで、若者をハードドラッグから隔離したのです。
オランダは「自由と寛容の国」であると言われていて、その国民性もこの合法化に拍車をかけたのではないでしょうか。
③ ウルグアイ
2013年12月、ウルグアイでは大麻の使用と商品化を合法化しました。
これは歴史上、世界中で初めてのことです。
その背景にはウルグアイは昔から麻薬の使用について他国ほど特に厳しくないことがあります。
麻薬密売は犯罪とみなされていながらも、個人的な使用であれば少量の不法薬物を所有することは犯罪とされませんでした。
そのため、法の下で大麻使用者が少量を所有できる状況にはあったが、合法的に手に入れる方法はなかったのです。
そこで2012年、当時のホセ・ムヒカ大統領は、政府の直接管理のもと大麻草の自宅栽培のみならず、公に直接販売することを認める法律を承認する意向を発表しました。
この理由としては大きく2点あります。
1点目は、麻薬密売人からの収入を取り上げることとなる合法化はウルグアイの治安がよくなると考えたため。
2点目は、質が保証された大麻を国民が合法的に製造もしくは取得できるようになれば、安全面や健康面としてもよい効果が期待できると考えたからです。
この法案のもと、販売は不法でありながらも、大麻の所有が合法であるという矛盾、大麻より中毒性があり有害なアルコール、たばこが合法である一方、大麻は違法である矛盾を解決できると考えました。
この政策はウルグアイ内外からすぐさま批判を受け、国民の過半数も反対意見でした。
それにもかかわらず、ウルグアイ政府は決定を妥当とし、2013年12月についに大麻の使用を合法化する法律を承認しました。
以上のように多くの批判を受けた合法化でしたが、この可決はどのような影響を生み出したのか、犯罪、消費、経済の側面から分析しましょう。
犯罪については、大麻合法化の影響が必ずしも直接的ではないため、大麻の使用と犯罪傾向の直接の関係を認めるのは難しいですが、2016年と2017年に国全体の犯罪率は下がっています。
またウルグアイの薬物委員会の報告によると2014年大麻使用者の58%は不法に薬物を取得していたが、2018年にその数は18%に減少した。
中学生の薬物使用に関する第7回全国調査ではその大麻使用率について変動はなく、国民全体の薬物使用に関する第8回全国調査では、初めて大麻を使用した平均年齢は2011年の18歳ごろから2018年の20歳と上がっています。
その一方アルコールやたばこは対象的で、2018年、ウルグアイの中学生の72%が飲酒の経験があり、ウルグアイ人の飲酒開始平均年齢は16.8歳である。
次に経済面については、内需により闇市場から収入を国に移行できただけでなく、大麻の製造工程に関連した雇用も生み出しました。
また現法案はウルグアイ国民向けに合法化したものであり、観光客は除外されています。
観光客も対象にすれば、大麻観光客が増え、国に大きな経済効果を生むことは間違い無いでしょう。
④ タイ
2019年2月に、東南アジアで初めて医療用大麻を合法化したタイでは、医師の処方箋があれば、患者は大麻由来の医薬品や乾燥大麻を使用することが可能になりました。
2021年には約700の病院・診療所に医療用大麻を処方する許可が与えられ、約700の大麻業者に生産・加工・販売のライセンスが付与されています。
タイ政府は医療用大麻ビジネスを経済成長にとって重要と位置づけ、将来的には大麻治療を国内のタイ人だけでなく、外国人観光客も利用できるように「医療用大麻ツーリズム」の準備を進めています。
⑤ 韓国
タイとほぼ時を同じくして、韓国は東アジアで初めて医療用大麻を合法化しました。
2018年7月、韓国の食品医薬品安全省(MFDS)は「治療の選択肢を広げるため」として、がん、癲癇、エイズ、多発性硬化症などの患者に大麻由来の医薬品の使用を認める決定をしました。
そして11月に国会が大麻の医療使用を認める麻薬取締法(NCA)の改正案を可決し、翌年2019年3月に合法化しました。
韓国は大麻由来の癲癇治療薬「エピディオレックス」、多発性硬化症治療薬「サティベックス」、抗がん剤治療の吐き気止めやエイズの消耗症候群の治療薬「マリノール」「セサメット」などを海外から輸入し、患者に提供しています。
タイと違うことは、韓国では乾燥大麻の使用を認めていません。
また、使用できる医薬品も限られているため、患者の支援団体などから、「もっと幅広い使用を認めてほしい」との要望が出ています。
タイや韓国で起きたことは他のアジアの国々にも影響を与え、合法化に向けた動きが活発化しています。
フィリピンは2019年1月、議会下院が癲癇、多発性硬化症、関節炎などの患者に大麻使用を認める「思いやりのある医療用大麻法(CMCM)」法案を可決しました。
現在は専門家により許可された場合のみ使用可能になっています。
また、マレーシアではアジアの中でも特に厳しい大麻禁止政策をとってきたことで有名だが、最近、閣僚が政策見直しを示唆する発言を行いました。
2019年6月、ズルキフリ・アフマド保健大臣が「過去40年間に及ぶ薬物戦争(厳しい薬物禁止政策)は失敗だった」と認め、「薬物の非犯罪化と、医療用大麻の合法化が必要となるだろう」と述べました。
その他、インド、スリランカ、ネパールなどでも合法化への動きが活発化しています。
このように、北米、欧州での嗜好用大麻合法化の理由は、「犯罪組織による流通を防ぐ」・「合法化した方が管理できる」が主であり、アジアの医療用大麻合法化の理由は「治療の選択肢を広げるため」が主でありました。
国際的な大麻関連業界向けのコンサルティング会社「プロヒビッション・パートナーズ(PP)」は、「アジアの医療用大麻市場は2024年までに58億ドル(約8,700億円)になる」と予測しています。
その大きな理由とされているのは、アジアで急速に進行している高齢化による医療費増大の問題です。
つまり、高齢者特有のさまざまな病気の治療に効果的とされる医療用大麻を合法化することで、各国は医療費を抑制でき、同時に合法大麻市場の成長を期待できるというわけです。
では次に合法国における大麻の歴史と現状について見ていきましょう。
① アメリカ
2023年でのアメリカでは、40州が産業用、医療用大麻が合法、西海岸を中心とした23州が産業用、医療用、嗜好用、全て合法になっています。
なぜこれほど大麻合法化が進んでいるのでしょうか。
アメリカでは薬物規制のガイドラインがあり、危険度、有害性、中毒性などから「スケジュールⅠ〜Ⅴ」に分類されています。
最も危険とされているスケジュールⅠは主にヘロイン、LSD、MDMA、大麻などが含まれ、スケジュールⅡにはコカイン、覚醒剤などが含まれています。
このガイドラインからは、覚醒剤よりも大麻が危険視されているものの、アメリカでは合法化が進んでいます。
この大麻がスケジュールⅠに含まれていることは、長年議論を繰り返しました。
1937年、初めてアメリカは大麻を規制し始めます。
連邦政府は、大麻に高い税金をかける「大麻課税法」を制定し、大麻を実質禁止にしました。
なぜ大麻を規制し始めたのかは明らかに発表されていないものの、一説では「禁酒法」が関わっていると言われています。
アルコールを含むお酒はアメリカで危険視され、お酒を禁止されていました。
その結果、裏組織が密造酒を販売するようになり、犯罪が増え、連邦捜査局が取り締まるようになりました。
この法律が廃止した後、連邦捜査局の仕事がなくなったため、大麻を取り締まるようになったと言われています。
またメキシコ移民がメキシコから大麻を持ち込んだ歴史から、メキシコ移民への反発によって大麻の取り締まりを強化したとも言われています。
アメリカでは高い税金によって規制する大麻課税法について議論が起こり、1970年に、当時のニクソン大統領は「薬物規制法」の中に大麻を入れ、法で規制するようになりました。
大麻が法で規制された2年後、これまで科学的に調査、解析されていなかった大麻についての報告書が提出されました。
この報告書では、「大麻の危険度や依存症はアルコールやニコチン(タバコ)に比べても薄い」とのことでした。
ニクソン大統領の思惑とは違ったこの報告書を、ニクソン大統領は受け取りを拒否しました。
これには大麻が反戦グループと密接に関係し、彼らの嫌悪感によるものと言われています。
またこの年から、他の薬品では治らなかった症状、病気が大麻の効果によって緩和、治療した症例が見つかり始め、これらを逮捕、監禁することは人道的なのかを問う議論が起こるようになります。
その結果、州によって合法化が進むようになり、2014年、合法州の連邦捜査局による逮捕を禁止しました。
その後も医療用大麻を必要とする人々、子供を持つ親達が医療用大麻解放のために立ち上がり、医療用大麻合法化運動を各州に広げていったのです。
それにより医療用大麻や嗜好用大麻の合法化する州が今でも増え続けています。
② タイ
アジアの国で初めて大麻合法化したタイでは、現在産業用、医療用大麻のみ合法で嗜好用の大麻は禁じられています。
しかし私がタイに渡航した時は、街中に大麻ショップが並び、道で利用している人も多く目にしました。
タイでは大麻の栽培や販売に関する規制はまったく実施されていません。
規制上のこの空白によって、タイ各地に販売店が続々と立ち上がり、予想していなかったようなかたちで大麻産業が成長しています。
しかし街中では堂々と大麻を販売し、警察官もそれを無視しています。
それはなぜか。
この背景には新型コロナウイルスが影響していると言われています。
観光大国であったタイは、新型コロナウイルスの影響から観光業が大打撃を受けました。
渡航規制も緩和されつつあり、大麻目的でタイに訪れる観光客も増えています。
そこで観光業を立て直す為、大きな経済効果を生む大麻産業を政府は黙認していると言われています。
③ オーストラリア
オーストラリアは2016年、THCを含む医療用大麻を合法化しました。
医師の処方箋があれば、慢性的な痛みを和らげる目的などで購入できます。
しかし、連邦レベルではTHCを含む嗜好用大麻は違法となっています。
この合法化の歴史として、オーストラリアではこれまでハードドラッグ(危険度や害が大き薬物)を使用する人が増加していました。
その対策案として政府が「メサドン」という薬物を薬物中毒者に投与することで、ハードドラッグの利用者、またそれに伴う犯罪を減少させています。
同時に犯罪組織による流通を防ぐ、合法化することで税金を回収することも目的としています。
これまで各国における大麻の歴史、現状について考察してきました。
日本が規制された理由、アメリカが規制された理由は全く異なっていました。
また生涯大麻経験者割合はアメリカ約40%、日本約1% であり、アメリカの規制だけを参考にしてはいけないと考えます。
日本という国風、国民性を考慮することが合法化に向けた大切なことだといえるでしょう。
日本の「大麻解禁」

では日本の大麻規制の課題と及び見直しはなにか。
大麻から製造された医薬品について、重度のてんかん症候群であるレノックス・ガストー症候群及びドラベ症候群の治療薬(エピディオレックス)は、アメリカを始めとするG7諸国において承認されています。
また麻薬単一条約における大麻の位置付けは「スケジュールⅠ」及び「スケジュールⅣ」という規制カテゴリーに位置付けられていたが、WHO専門家会合の勧告を踏まえ、2020年の麻薬委員会(CND)の会合において、スケジュールⅣのカテゴリーから外すことが可決されました。
これにより、依然として、スケジュールⅠとしての規制を課すことは求められつつ、 医療上の有用性が認められました。
日本においても、エピディオレックスについて、国内治験が開始されています。
一方、現行の大麻取締法においては、大麻から製造された医薬品について、大麻研究者である医師の下、適切な実施計画に基づき治験を行うことは可能ではあるものの、大麻から製造された医薬品の施用・受施用、規制部位から抽出された大麻製品の輸入を禁止しています。
そのため仮に、医薬品医療機器等法に基づく承認がなされたとしても、医療現場において活用することは認められていません。
イスラエルは医療用大麻先進国と呼ばれ医療用大麻の研究が進んでいるが、日本では研究用での大麻の使用も禁止されているため、調査することもできないのが課題の一つと言えるでしょう。
また第三章でも取り上げた大麻利用の検挙数の増加、使用罪がないことで使用へのハードルを下げていること、大麻への誤認、その原因となるSNS等の「コミュニティサイト」の在り方も課題だと考えます。
上記の課題を踏まえた上で、2023年10月24日、大麻取締法などの改正案が閣議で決定しました。
改正案内容は大きく2つあり、①大麻草を原料にした医薬品の使用を認めること、②すでに禁じられている「所持」や「譲渡」に加えて「使用」も禁止することです。
改正の理由として、①は大麻草を原料にした医薬品は、欧米各国で承認され、難治性の癲癇の治療目的などで使用されているが、国内では大麻取締法で規制されていることから、医療関係者や患者から解禁を求める声が出ていたため。
②は若者などが大麻を乱用するのを防ぐため、誤認を減らすためです。
また上記の2つに加えて、③繊維や種子の採取、研究目的にのみ認められている大麻草の栽培を、医薬品などの原料を採取する目的でも認める。
④大麻を「麻薬及び向精神薬取締法」で規制する「麻薬」に位置づけることも決定しました。
これまでを踏まえ、当記事の本題である日本で「大麻解禁」を検討し始めた理由について考察していきます。
上記のように医療用大麻の合法化は現状進んでいます。
現在癲癇患者は国内で100万人いるといわれ、そのうち10-20万人の患者は発作が抗癲癇薬の服用で抑制できずに慢性化するいわゆる難治性癲癇で困っています。
これらの難治性癲癇の中には薬で発作を抑制できない者もいます。
今回の改正案が可決され、難治性の癲癇治療などに使用するための大麻草を原料にした医薬品の使用が可能になれば、2万人から4万人が対象になると見込まれています。
また医療用大麻で効果が期待されている主な病気の国内患者数、緑内障は約500万人(厚生省)、がん治療で抗がん剤を使用している患者約70万人(厚生省)、またうつ病を有する患者は新型コロナウイルスの影響で急増し、約2000万人(経済協力開発機構の「メンタルヘルスに関する国際調査2021」)いると言われています。
医療用大麻が合法化した場合、これだけの人数が対象になるのです。
また大麻は100種類以上の成分があるだけでなく、相互作用によって様々な病気に効くとも言われています。
これだけでも医療大麻を合法化する大きな理由と言えるでしょう。
また同じく麻薬の一種であるアヘンを原料として作られる鎮痛薬モルヒネが医療用で使われていることもこの法改正を後押ししています。
2023年12月6日、参院本会議で大麻取締法改正案が、可決成立しました。
今回の法改正から、大麻と大麻由来のTHCを「麻薬」と位置づけ規制することになり、「部位」による規制から「成分」による規制に変わりました。
加えて、免許所持者は大麻草から製造された医薬品施工などが可能になりました。
また既に罰則の対象となっている大麻の所持・譲渡に加え、大麻を「使用」することも禁止され、使用した場合には罰則の対象となりました。
この法改正は2024年12月12日に施工されています。
11月22日には、厚生労働省はいわゆる「大麻グミ」に含まれている大麻成分に類似した成分「HHCH」を「指定薬物」と指定し、12月2日から、この物質ならびにこの物質を含む製品について、医療等の用途以外の目的で製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されました。
医療用大麻の実例

① 5歳の少女のシャロットちゃん
シャロットちゃんは生後3ヶ月からドラベ症候群という重度の癲癇発作に苦しめられてきました。
彼女の発作は毎日続き、1日数十回に及ぶこともあり、その度に大声を発し、髪の毛を引っ張り、頭を床に打ちつけました。
あらゆる処方薬を試し、鍼治療や自然食療法も試したが発作は抑えられず、ひどく痩せ細りました。
次に発作が起きれば死ぬかもしれないという状況まで追い込まれた時、医療用大麻を使用しました。
当時5歳だった彼女は乾燥大麻ではなく大麻成分入りオイルを舌に数滴垂らしました。
これを機に彼女の発作は一切なくなったのです。
それまで1日何十回も起きていたのに。それから1年後、彼女はすっかり元気になりました。
以前はチューブで栄養補給していたが、普通に食事ができるようになり、話すことも歩くこともできるようになりました。
② 大麻を吸ってエイズを克服した検事キース・ヴァイズさん
サンフランシスコ検察庁で検事を務めるキース・ヴァイズさんはHIVの感染を告げられました。
なかでもエイズ患者の末期症状とされる全身消耗症候群を発症し生命の危機にさらされ、体重は激減し、免疫力を示すT細胞は健康な人の10分の1以下に減りました。
発症当初はエイズ治療薬と体力増強剤を投与していたが、ほとんど効果はありませんでした。
そこで検事だった彼は医療用大麻の使用を決意しました(1990年代、サンフランシスコ市では、「医療用大麻の使用者を黙認する」と制定されていた)。
医療用大麻を使用するようになり、食欲が増え、処方薬の副作用による悪寒や嘔吐も止まりました。
彼はそれから医療用大麻を処方した医者、患者の逮捕に関する裁判を起こし、原告側で勝利しました。
③ 大麻クッキーで失明の危機を逃れた女性エルビー・ムシカさん
フロリダ州に住む銀行員のエルビー・ムシカさんは緑内障と診断されました。
この症状は眼球内の圧力が高まり、重症になると失明の恐れがあります。
彼女は約1年半、地元の眼科医で治療を受け、処方薬を服用していたが、副作用がひどく精神的にも落ち込むことが多かったそうです。
そんな時友人から、大麻に眼圧を下げる効果があることを聞き、大麻成分入りのクッキーを食べることにしました。
それから3ヶ月後、眼圧がほぼ正常値まで下がり、緑内障が治りかけていました。
しかし法律で禁止された大麻を使用していることへの罪悪感、いつ逮捕されるかもしれないという不安により、使用をやめました。
すると1週間もしないうちに眼圧は再び上昇し、両目ともほぼ最悪の状態に戻っていました。
眼圧硬化剤も試すも効果はなく、再び大麻クッキーを食べると正常値に戻りました。
しかし主治医は医療用大麻を頑なに認めず、手術を強行しました。
結局彼女は10回以上手術を受けたが、その甲斐なく、右目を完全に失明してしまいました。
彼女は「後から考えれば、大学病院など行かず、大麻クッキーをずっと食べていれば右目を失わずにすんだかもしれない。残った左目はどんなことがあろうと、自分で守る」と言いました。
その後彼女は、連邦政府が例外的に医療用大麻を認めた「コンパッショネート・ユース」プログラムの適用を受けることができました。
おわりに
これまで大麻の歴史、危険性、法改正等について書いてきましたが、みなさんは「大麻」のイメージが変わったでしょうか。
またこの法改正についてどうお考えでしょうか。
私の意見としては、今後日本は、医療用大麻合法化の法改正、嗜好用大麻非合法化は継続すべきだと考えます。
上記で記載した、医療用大麻の実例はほんのひとにぎりにすぎませんが、大麻が患者の命を救っているのは確かです。
また少子高齢化が進む日本において、高齢者に起こりやすい体の痛みや痙攣、不眠、食欲不振などを改善し、処方薬の使用量を減らすのに役立つ大麻は今後の日本で活躍するのではないでしょうか。
米国の経済ニュース専門チャンネルのCNBCは、「アジアで勢いを増す医療用大麻市場」(2019年7月14日)と題するリポートのなかで、世界一高い日本の高齢化率や医療費増大の問題について触れ、「日本は医療用大麻の巨大な消費市場になる可能性が高い」と報じています。
これらの事例のように、大麻によって命を救われた人たちをあなたたちは裁き、厳しい罰則を科すことができるでしょうか。
それはとても人道的とは言えないでしょう。
少なくとも医療用だけでも認めることを検討しても良いのではないだろうか。
もちろん合法化された時は、医者の処方箋が必須や、使用後の運転の禁止など、厳しい法整備を設けることが重要であると考えます。
また先述した通り、日本では研究すら厳しく制限されているのが問題だと考えています。
大麻成分を使って多様性硬化症の治療効果を研究しているチームは、動物実験で治療効果があることを示唆する結果を得ましたが、大麻成分を人に投与する臨床試験は禁止されているため、それ以上の研究を進めることができず、途中で解散してしまいました。
これについては今回の法改正を国会が認め、大麻に関する研究が進むことを期待するのみです。
また臨床試験などを通し、統計学的な処理を伴ってエビデンスを出すことも、今後の合法化に向けた不可欠な取り組みでしょう。
また嗜好用大麻の非合法化の継続については日本の国民性を考慮してのことです。
もちろん嗜好用大麻合法化によるメリットもあります。
大麻はアルコールやニコチンより中毒性も依存性も低いという研究結果も出ています。
また現にアメリカでは、州の税収が伸び、2014年度の大麻販売による物品税と売上税の税収は約4,400万ドル(約66億円)に上り、その半分が公立学校の建設費に、残りは未成年者の大麻乱用防止教育に充てられることになりました。
しかし日本国内で同じようなことが起きるとは思いません。
そもそも大麻はタバコと違い、後処理が非常に簡単で誰でも栽培できてしまいます。
勤勉である日本人は大麻を個人で取り扱い、法を抜ける人は必ずいるでしょう。
また嗜好用大麻の合法化による観光業での経済効果も見込まれますが、大麻で外国人を集めるのは本当に在るべき日本の姿なのでしょうか。
日本が外国に誇るものは、文化であり、景色であり、人だと私は考えます。
法律とは願いであり国家がその国民に望む在り方の理想を形にしたものでもある。(キングダムが好きな人は誰の名言かわかるでしょう。笑)
「日本のようなストレス社会には絶対必要」という声もあるが、嗜好用大麻の合法化は私たちにとって理想の形なのか深く検討する必要があるでしょう。
また遵法精神が強い日本人は「大麻=合法」となった時、大麻は完全に安全なものと誤解する人が多く生まれるでしょう。
日本ではこれまで、2011年に起きた池袋暴走事件、2014年に起きた危険ドラッグ刺傷事件など、危険ドラッグ、脱法ドラッグに関する事件が多々起きました。
それは「脱法=成分が弱い」と考える人が多く、遵法精神の強い日本人は特に「脱法」という言葉に安心感を覚えやすいのです。
大麻と同じ麻薬の一種であるアヘンを原料としてつくられる鎮痛薬モルヒネを日本人は使いたがらないのです。
モルヒネは癌の疼痛緩和などに大きな効果を発揮するが、日本のモルヒネ使用量はカナダ、オーストラリアの約7分の1、アメリカ、フランスの約4分の1と、他の先進国と比べて著しく少ない。
これは日本人の麻薬に対するネガティブなイメージの固定概念が強すぎるからです。
小学校から「大麻=ダメ。ゼッタイ。」と教わり、薬物の違法性、危険性のみを知ることになります。
インターネットが普及し、人々が大麻に関する情報を簡単に入手できる現代で大事なのは、どれが正しく間違っているのか取捨選択し、自分自身で大麻についての理解を深め、自分で考えて判断する力を育むことだと思います。
今後、大麻が日本に大きな影響を与えるのは明確であり、今回の2024年改正法施行以降、「大麻の行方」を見守る必要があるでしょう。
みなさんの意見もぜひ教えてください。
下記に参考文献をのしておきますので、もっと詳しく知りたい方は是非チェックしてみてください!
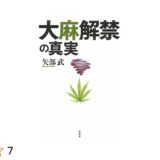
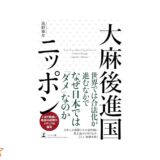
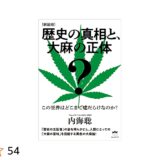
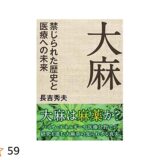
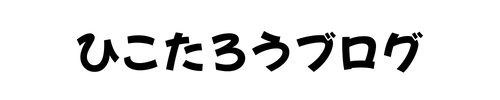


コメント